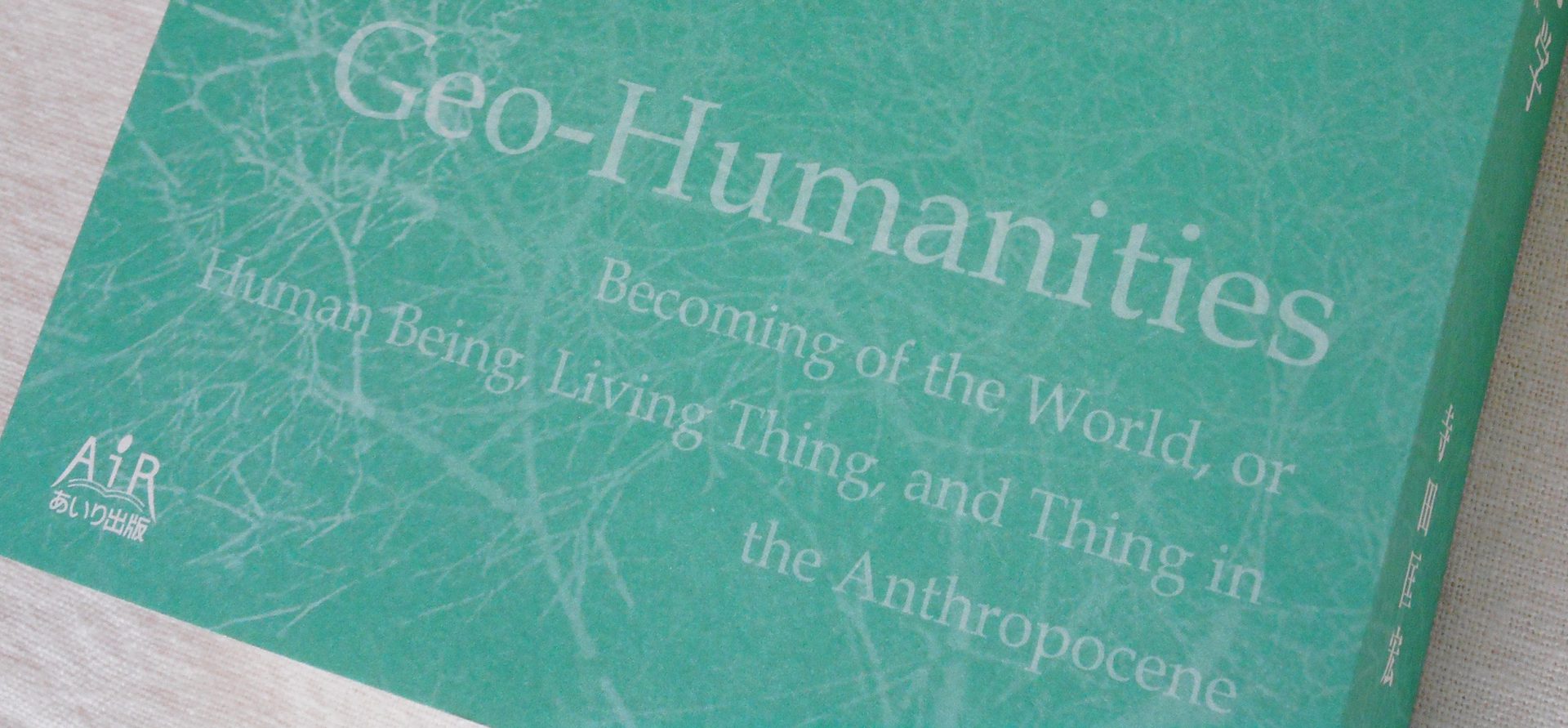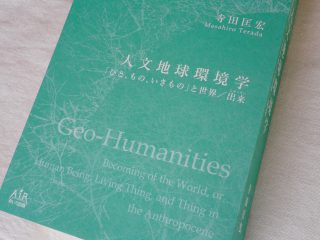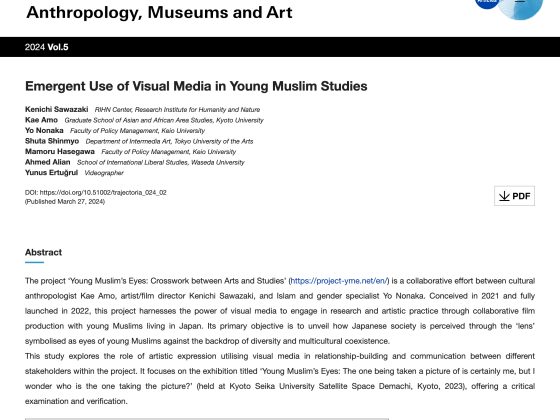リビモン・メンバーの寺田匡宏の新著『人文地球環境学――「ひと、もの、いきもの」と世界/出来(しゅったい)』がこのほど刊行されました。そこで、刊行を機に、寺田さんにこの本についてインタビューを行いました。(聞き手・編集部)
『人文地球環境学』著者・寺田匡宏インタビュー
「文」から考える地球と人間
――まずは、この本を書こうと思ったきっかけから教えてください。
寺田 そうですね。この本を書こうと思ったのは、ひとつは、このような本があまりないことです。
地球環境学の本は数多くあるのですが、人文の方向から地球環境を論じた本があまりない。社会一般では、環境学というと、理系の学問だと思われています。環境学を研究していますというと、気候温暖化の研究や、森林の研究、水質の研究などですか、といわれる。環境を定量的に測定しそのメカニズムを明らかにする自然科学が連想されやすいようです。そして、事実、その側からの環境学の研究が量的にも中心であり、かつその進展は目覚ましいものがあります。それらをまとめた本は数多くあります。
あるいはまた、持続可能性研究や、住民参加型研究といった方向からアプローチする分野も、環境学の中では大変大きなウェートを占めていて、それに関する本も多いです。政策としての環境研究ともいえるかもしれません。「SDGs(国連持続可能な開発目標)」などは人口に膾炙し、お店屋さんやバッジなどでマークをさまざまなところで見かけます。環境問題というと、微小プラスティックやレジ袋有料化などの問題ととらえられることもある。
そんな中、人文の方向から、地球環境についてのアプローチについては、社会的にイメージがわきにくいようです。そして、実際、そのような方向性から書かれた本、そのような研究を総括したような本は実はあまりないのです。
人文の方向からというと、たとえば、ひととものの区別、ひとと生き物の区別が揺らいできたり、あたらしいオントロジーが提唱されたり、地球環境に関する公平性や正義についての新しい視野が生まれたりしていますが、それらを含みこんで、いったい地球環境全体を人文の視点からどうとらえればよいのかということを総体的に扱ったコンパクトな本は実はありません。そこで、このような本が必要ではないかと思っていました。
――なるほど。たしかに、人文の領域でのさまざまな研究の進展は目覚ましいので、それを取り入れた地球環境学のアップデートは必要ですね。
「人新世」とジオ・アンソロポロジー
寺田 そして、もう一つきっかけがあり、それは、外からの刺激です。
いまヨーロッパでは「ジオアンソロポロジーGeoanthropology(人間地球学)」という学門の形成が進んでいます。本書の英文タイトルは「ジオ・ヒューマニティーズGeo-Humanities」ですが、そのような潮流に、それとは異なった視点からコミットできないかというのがありました。
この「ジオアンソロポロジー」というのは、ドイツ・ベルリンのマックスプランク科学史研究所ダイレクターのユルゲン・レン博士によると、「人新世に至った経緯を研究する学」です(ユルゲン・レン『知識の進化史』プリンストン大学出版局、2020年、英文)。
「人新世」という語は、斎藤幸平さんの『人新世の資本論』(集英社新書、2020年)がベストセラーになり、広く知られるようになりました。近年、地球環境をめぐって提唱されている新しい地質年代区分です。地球環境危機の時代である今日を、人間が地質年代にまで影響を与えている時代として、「完新世」に代わって「人新世」という語で呼ぼうというもの。レンさんは、そのような地質年代規模の変動に至った経路を探る学を「ジオアンソロポロジー」と言っています。
――『人新世の資本論』がベストセラーになった背景には、コロナ禍という環境の新しい危機の中で、地球と人間環境の関係を誰もが問い直さなくてはならなくなった状況もあるように思いますが、まさに、そのような問題意識ともつながりますね。
寺田 そうだと思います。「ジオアンソロポロジー」でいう、ジオとは地球で、アンソロポロジーとは人間学という意味。この「アンソロポロジー」という語は、今は「文化人類学」や「民族学」などの比較的限定された学問を指しますが、もう少し古い時代、19世紀ごろだと、もっと広く人間と外部世界のかかわりを探求する学を意味していました。
たとえば、18-19世紀に活躍したドイツの哲学者イマニュエル・カント(1724-1804年)にもこの「アンソロポロジー」を論じた論文があります(1798年)。カントは、哲学者ですが、実は自然科学とりわけ、物理学、宇宙論、数学にも造詣が深く、『純粋理性批判』(1781年)には随所で物理学や宇宙論の話題が出てきます。彼の『純粋理性批判』では、超越的理性が論じられているのですが、その発想の源泉となったのは、ニュートンの絶対空間と絶対時間で、同書で非常に大きな意味を持つ四つの二律背反を論証した箇所では、「世界には始まりはあるのか」「世界は部分でできているのか、それとも一つなのか」など、現代の宇宙論とも関係する議論が行われています。カントは30代の若いころには、「ニュートンの基本法則をもとにした自然史一般ないしは宇宙に関する法則、全ての世界構成物の起源のメカニズムの探求」(1755年)という論文も書いています。
彼は、50代くらいには、「アンソロポロジー」を大学で講義していましたが(1772年の冬学期―)、それは「ジオグラフィー」つまり地理学とセットになっていた。
カントの「アンソロポロジー」を論じた論文は、その大学の講義録でもありますが、それを読んでみると、現在の文化人類学や民族学などというよりも、人間の認識や性質や傾向を論じるものです。それは、物理学的法則が貫徹するこの世界の中において、自由意志を持った人間がどのような特質を持っているかということを探求しているものでもある。
そのように「アンソロポロジー」とは、初発の時点では、この世界の中の人間の位置づけを探ろうとする学であったといえます。カントは、カントの時代の自然科学のとらえた世界の中での人間の位置づけをとらえようとした。
一方、現在形成中の新しい学問である「ジオアンソロポロジー」は、現在が人新世であるという自然科学からの警鐘を受け止めて、その中での人間の位置づけを考えようとしている学である。「人新世」という語が提起されたことで、新しい人間と地球の関係が問われている。ジオアンソロポロジーは、それを示しています。
ただ、ヨーロッパにおける人間の位置づけとアジアにおける人間の位置づけは少し違います。そんな中で、東アジアにおける人間の立場から「ジオ」つまり地球環境を考えてみればどうだろう、という思いもありました。
文を通じた天と人の照応
――それが、本書でいう東アジア漢字世界の「文」を通じた地球と人間の照応という考え方ですね。
寺田 そうです。「文」というのは非常に興味深い語です。
現在では、「文」と聞いてぱっと思い浮かぶのは、「文学」や「文章」などのように、人間のが、おもに言語を介して行う知的な行為に対して用いられる用法ですが、しかし、実はそれ以外にも、「天文」、「水文」などの語もあります。その場合の「文」とは、「模様」や「パターン」や「様子」なとどいうような意味があります。
東アジア漢字圏には、「人文(じんもん)」、「天文(てんもん)」、「地文(ちもん)」というセットになった語があります。東アジアの伝統思想では「天」は非常に大きな意味を占めます。「天命を知る」というような語もあるように、天がある意味で普遍的な価値を体現しており、そこから「理」や「気」といった世界をつらぬく原理が世界に分配されるという考え方です。
「天文」と「人文」「地文」という語は、それを示しており、天と地、天と人が照応していることを言う。つまり、「文」を通じて、人間は世界と通路を持っているという考え方です。
――たしかに、天文学という学があり、水文学という学もあります。そして人文学という学もありますが、そういう背景があったのですね。
寺田 はい。それは、漢字語の世界の学問の区分の仕方であるともいえるでしょう。それは、文系、理系という語にも関係しています。先ほど「理」という言葉を用いましたが、理と文が対照的な存在としてとらえられているところに、文系、理系という漢字での世界のとらえ方の特徴があるように思います。
一方で、学問の世界には、「学際」というような区分があります。西洋起源の諸学問は、学問の方法でしっかりと分けられています。しかし、地球環境学のような複合的な現象を扱うためには「学際」が必要になってくる。
そのようなとき、東アジア漢字圏の伝統的な考え方である「文」を起点にして、人文の立場から地球環境を考えると、西洋起源の学とは異なった見方ができるのではないか、という思いもあり、本書では「人文」を強調しています。
――なるほど。人文学というのは、そのような背景があるのですね。
寺田 「文」に注目することは、近代の学問の在り方そのものを再考するものでもあるともいえます。
近代の学問、あるいは近代の科学とは、人新世を導いたものでもあります。さきほど、「ジオアンソロポロジー」という学について紹介する中で、ジオアンソロポロジーは「人新世に至る経路を探求する学」という定義があることを紹介しました。それに対応していうと、「人文地球環境学は人新世を「文」という視角から批判的にとらえる学」であるといえるかもしれません。
自然は語るか
――なるほど。「文」とは、言語行為であると同時に、世界への向き合い方でもありますね。言語行為というと、本書の中では、「語り」という言葉がよく出てきます。そういう言葉は、地球環境学ではあまり扱われることはないように思うのですが、どうでしょうか。
寺田 いえ、そんなことはないですよ。環境をだれが、どう語るのかは、今とても大きな問題となっています。語りは、「ナラティブ」ですが、ナラティブの問題は常に問われています。環境は様々な立場によってさまざまに異なって認識されます。その異なったありようが問題となってきているのです。
――ユクスキュルのいう「環世界」ですね。
寺田 そうです。ダニにはダニの、犬には犬の、そして人間には人間の世界の認識の仕方があります。そして、人間の世界の認識の仕方といっても、文化により様々な認識の仕方もある。
――本書の中で、「いきものは語るか」という問題が興味深いです。
寺田 ちょっと考えてみましょう。いきものは、語るのでしょうか。
この世界には、さまざまな「お話」がありますが、そのお話の中では、いきものは語ります。お話の中で、それはごく自然なことのように思えますが、しかし、科学の世界では生き物が語るなどと言えば、相手にされません。
けれども、はたしてそれはそうなのか。フランスの人類学者フィリップ・デスコラは、『自然と文化を超えて』の中で、そのような「科学主義」は決して普遍的でもなければ、論理的に正当化できるものでもないことを、論理学の「対当関係」を用いて明らかにしました。
ここでは科学主義と言っていますが、デスコラはそれを「ナチュラリズム」と言っています。「ナチュラリズム」は文字通り訳すと「自然主義」なのですが、「自然主義」とは、日本語では、大変、多義的で、「自然主義文学」などという語もあり、そう訳するとちょっとわかりにくくなります。「科学主義」と訳した方がわかりやすい。「ナチュラリズム」とは、今現在の科学が「自然を自然としてとらえているようなとらえ方で世界を見る見方」ということです。ですから、「科学主義」の方と訳せる。
世界には、同じように例えばあるいきものや樹木を見ても、それを「カミ」としてとらえたり、「トーテム」としてとらえたりする見方もあります。「アニミズム」や「トーテミズム」です。しかし、科学は、それらを否定し、あるいきものや樹木を「自然物」として見る。それが「ナチュラリズム」であり、すなわち「科学主義」です。
デスコラが明らかにしたのは、「科学主義」というのは、ある一つの世界のとらえ方にしか過ぎないのであり、それは、アニミズムや、トーテミズムなど、いきものと人の多くの関係の中の一つにしか過ぎないということです。科学主義だけが合理的、普遍的で、アニミズムやトーテミズムが非合理的で非普遍的であるとは言えない。アニミズムが非合理的ななら、科学主義も非合理的である。その意味では、いきものも語るといえます。本書で語りというときには、そのような立場を意識しています。
――それは、先ほどの「文」の問題ともつながりますね。「文」は言語的なものであるだけあり、人間に特有のものであるだけではなく、もっと広い、世界が世界のあり方を「語る」方法の一つであるともいえる。
寺田 まさにその通りです。科学の世界でも、バイオセマンティクス、バイオセミオティクスというような分野が現れてきていますが、それとも通じる話だと思います。
アガンベン、災厄、世界
――学問の中では、様々な新しい潮流が生まれてきているのですね。そういえば、本書刊行の5年前に刊行された寺田さんの前々著『人は火山に何を見るのか』(昭和堂、2015年)の英文タイトルは、「自然と人間の’新しい学‘に向かってTowards a New ‘Scienza Nuova’ of Humanity and Nature」と銘打たれていました。新しい学の方向性は見えてきましたか?
寺田 『人は火山に何を見るのか』をまとめる原動力となったのは、ベルリンでのアガンベンの『開かれ』との出会いでした。
2014年に人新世をめぐるあるワークショップのために、ベルリンに行きましたが、そこで、ワークショップの関連文献を集めた小さなミニ・ライブラリーが臨時に設けられており、アガンベンの『開かれ』に出合ったのです。
ジョルジュ・アガンベンはイタリアの哲学者で、神学者ではありませんが、キリスト教的な様々な概念を哲学の中に導き入れて現代の問題としてきた研究者です。
それまでも『ホモ・サケル』や『アウシュヴィッツの残りのもの』などの作品を読み、魅了されてきましたが『開かれ』もその一つでした。
『開かれ』は、ドイツの哲学者のマルティン・ハイデガーの「世界への開かれ」という概念を手掛かりに、人間と世界の関係を探求した本です。その中には、先ほども話題に出てきた「環世界論」のヤコブ・フォン・ユクスキュルなども引用されています。
けれども、正直言って、この本を読んだときには、この本が環境学と関係するという思いはありませんでした。というか、日本語の世界では、アガンベンの『開かれ』を環境学の問題としてとらえるという発想は全くないように思えた。
ぼくが、その時、アガンベンを読んでいたのは、地球上の様々な災厄をどう考えるかという文脈からでした。通常は、自然災害と人為的災害は区別されますが、災厄、あるいは災いを大きくとらえた時、実は、「禍」の「禍性」とでもいうものが問題になるのであり、人為的災厄と自然的災厄の区別はあまりなくなる。となると、アガンベンが扱っている問題は普遍的な問題のように思えました。彼は、アウシュヴィッツのことを論じながら、同時に、ユクスキュルのことを論じている。人為と自然という区分を超えて普遍的に考える道筋を彼は示しているように思えたのです。
だが、日本ではそのような考え方はあまりないように思えたし、そのような論じ方の道筋はなかった。それを自分のものとしてどう考えればよいか、考えあぐねていたのです。
しかし、ベルリンのそこでは、アガンベンと地球環境がしっかりと結びつけられていた。
アガンベンの『開かれ』は決してわかりやすい本ではありません。そもそもアガンベン自体がかなり難しい思想家です。そのような思想家の本を、人新世をカギにすることで新たに読もうとする動きがある。それには、とても力づけられました。「人新世」という概念は、自然科学由来の概念で、自然科学の精髄ともいえる「地球システム科学」をベースにしている。一方のアガンベンは、言ってみれば人文学の極地です。その二つが、そのベルリンのワークショップでは、しっかりと結びついているように見えた。しっかりと組み込まれていた。地球の反対側のここにヒントがあった、という思いでした。そして、そこから、新しい学が何か生まれているような気がした。それを予感としてあの本では「新しい人間と環境の学に向かって」と表現したのです。
新しい学
――なるほど。考えてみれば、いま、学の過渡期であり、「人新世」の提唱もそうですが、様々な新しい動きが随所に萌芽的に存在していますね。
寺田 そうです。人文学に限ってみても、ブリュノ・ラトゥールのアクター・ネットワーク理論、人類学におけるマルチ・スピーシズ民族誌、STSにおけるサイボーグ宣言、形而上学におけるもの志向のオントロジー(存在論)など環境に関する新たな動きがあります。それらを環境学に取り入れるべきではないかという思いがありました。
さらにいえば、これまで環境学にしっかりと取り入れられてきたとは言えなかった重要な学もあります。例えば、オギュスタン・ベルクのメゾロジー(風土学)、藤井貞和の「物語学」、今西錦司と伊谷純一郎を始祖とし、河合雅雄、山極寿一、菅原和孝などによってはぐくまれてきた霊長類学、中沢新一のレンマ学、レヴィ・ストロースの神話学、アマルティア・センのケイパビリティ論、ジョンロールズの正義論、杉原薫らの生存基盤指数、総合地球環境学研究所で推進されてきたエコ・ヘルスやエリア・ケイパビリティ論。それらをしっかりと組み込んだ地球環境の人文の学が必要ではないかという思いがあったのです。
――大きな志ですね。しかし、それらを統合したり、組み込むことは可能なのでしょうか。
寺田 そうかもしれません。ただ、それらを並べただけでは、単に、並列であって学ではないのも確かです。新しい「学」にするためには、何かの筋を一本通さなくてはならない。それを今回は「ひとものいきもの」と「世界/出来」という二つの切り口からおこなってみました。
「ひと、もの、いきもの」
――なるほど、副題にもなっている「ひと、もの、いきもの」と「世界/出来」ですね。「ひと、もの、いきもの」の方は、なんとなくわかります。人間と生物、物質が作り上げるのが環境であり、その環境の在り方を考えるということでしょうか。
寺田 そうですね。そして、それと同時に、それらそれぞれの間の境界線の在り方を再考していくということ。
――境界線ですか。
寺田 そう。ひとと他のいきものの間に境界線はあるのか。あるいは、いきものとものの間に境界線はあるのか。考え始めると難しい問題です。先ほど、メゾロジーという言葉を用いましたが、はっきりと境界があると考えるアリストテレス以来の世界の見方に対して、ナーガールジュナのような境界線はなく、中間領域がグラデーションとなって連なっているという考え方もある。そして、そのような境界の在り方自体が問われているのが、現在の環境をめぐる状況ではないかということです。
「世界/出来(しゅったい)」
――なるほど。では、もう一方の「世界/出来」についてはどうでしょう。ちょっとわかりにくいですが。
寺田 世界とは取り巻くものですが、それは、その都度その都度カテゴリー化されてゆくものではないかという思いがあります。つまり、ひとといきものの間に線を引くというカテゴリー化も、いきものともののあいだに線を引くというカテゴリー化も、その都度、世界としてあらわれるもの。それを「出来(しゅったい)」と言っています。そして、そのような出来の瞬間に目を凝らすことから見えてくるものがあるのではないか、そのような注意力が必要ではないかという思いがあります。
本書のカバーや扉には、アーティストのロヒニ・ディヴェシャーさんの「樹現」という作品を掲載させていただきました。ロヒニさんとは巻末で対談もしていますが、彼女の作品はまさに、そのような「世界と出来」を体現したもの。
彼女は、それを「可能性たちの温室」と呼んでいます。世界とは様々な可能性である。可能性に開かれているものとして世界をとらえることは、世界に対する能動的な態度をはぐくむものでもあります。様々な可能性があり得ると考えることは、オルタナティブを想像することでもあります。
地球環境学という学は、未来にかかわる学です。未来の持続可能性という問題を地球環境学は強く意識します。もちろん、それだけが、地球環境学のレゾン・デートルではなく、この世界における人間の位置を知るという目的もありますが、それとても、やはり、人間がどう生きるか、どう生きるべきか、という問題と切り離されることはない。
そう考えた時、世界と出来とのかかわりというのは、まさに地球環境学の根源的な問題意識であるともいえる。
そして、そこに現れるものを育ててゆく。人文地球環境学もそんな学ではないかと思います。
地球のナラティブ
――なるほど。終わりなき道のようにも思いますが、大切なことですね。最後に、本書は地球のナラティブシリーズの第2回配本として刊行されました。寺田さんは、このシリーズのシリーズエディターでもありますね。このシリーズの展望を教えてください。
寺田 地球のナラティブシリーズは、第1回の配本が清水貴夫『ブルキナファソを喰う!』で、おかげさまで好調なスタートを切りました。主要紙の書評に取り上げられるなど、読者からも温かく迎えられました。それを受けての第2回配本となり、本書もそれに続きたいところです。
今回の本は、第1回配本に引き続き、造本は綴水社の上瀬奈緒子さん、装丁は象灯舎の和出伸一さんに担当していただきましたが、美しい本に仕上げていただきました。第3回配本、第4回配本と、準備が進んでいますので、このままこのペースで刊行が続けることができれば、と思います。
――期待しています。お話をどうもありがとうございました。
寺田匡宏著『人文地球環境学――「ひと、もの、いきもの」と世界/出来(しゅったい)』あいり出版、2021年。2000円+税。